



2002/05/02 東京都写真美術館
→ 本当に起こっていること、あるに違いないと確信していて無意識に探しているもの、そういうものになかなか出遭えない不幸は度々強弱は別として日常の中に存在している。その不幸が同じことで多くの人に重なると、期待していた対象に裏切られた気分で鬱陶しいものになってしまう。東京のメディアアートシーンはまさにその不幸に見舞われている。 「メディアアートはつまらないし鬱陶しい」そういう声は、日常会話での決まりごとのように普通の認識になってしまっている。ロンドンやニューヨーク、リンツや台北などで、イイ!、新鮮!と呼ばれているものもホームグラウンドでは、鬱な存在なのだ。その不幸はオーディエンスだけでなく、多くのアーティスト自身も認識(まさに海外で力が認められた人は特に)し始めている。 出遭えるようにすれば不幸はどこかにいってしまう。そして、今までの東京になかったアートイベントが始まった。
この項は、オンライン・デザイン・マガジン『shift』2002年6月号に寄稿した原稿をもとにしております。


森羅万象との売り言葉に買い言葉
→今、電子メディアをつかった日本の芸術家たちは、これまでになかったアプローチによるオーディエンスや社会とのコミットメントを開発しようとしている。現代芸術の発想法から生まれた生立方体のロボットの開発(椿昇)、電子工作教育玩具の開発(森脇裕之)、マルチプルな造形作品になるTシャツ(クワクボリョウタ)など、コンセプチャルなものから日本で今一番必要だといわれつつある科学教育、それにデザインや雑貨まで、アーティスト自身がセルフプロデュースを行うことが、美術館やギャラリーで展開して行くのと同じ重み、ときには現実との係わり合いを求めることを意図することでそれ以上の重みを持った活動としつつあるのだ。このコミットメントを求め、開発し、新しい活動の回路と基盤を開拓するために、作品やプロジェクトに語らせるのでなく、自身が抱えている構想やアイディア、そしてそのリアリティーをオーディエンスに直接働きかけたいという意欲が、この脱ホワイトキューブのフロンティアを見出し始めた日本のパイオニアたちに芽生え始めている。
→「売り言葉に買い言葉」という諺が日本にはある。ブレークスルーしそうなことには対象である人々も同様の気持ちを持ち、自ずから活発に流通するというこの意のように、アートを求めるオーディエンスも、今までのようなある種のプレッシャーを必要以上に感じさせる現代芸術の中のホワイトキューブの中だけではない、アーティストそのものの才気に触れ、日常の中に在りたいという気持ちを持っている人が少なく無い。
→アートに対してある種の鬱屈した気持ちを持つ人が多い中で、一方で、デザインを好み、日常のあらゆる局面にデザインを求める人々が多い日本の現状は、言うなれば出遭いを求める人々の声なき要望の多さの反映でもある。息づかいがし、共感できたり、自身の文化の糧となるアートをささやきかけてくれるアーティストとのであいを待ち望んでいるのだ。


「新しい」アートイベントのデザインに着手
→「メディア芸術家が持つそのプランはオーディエンスに働きかけることによって活きてゆく」、「そしてオーディエンスは魅力を実感できる理解と思考の場を求めている」この、可能性と欲求、そして説得力が生まれるメルトダウンの機会こそが、不幸を溶き、知的な幸福感と、オーディエンスとアーティストそれぞれが参加者として新たなリアリティーを作り出して行く創造的参加のマイルストーンになるのではと、私はその新しいアートイベントの「デザイン」に着手した。
その新しいアートイベントに課した名は「アートデモ」、アーティストによるプロジェクトデモンストレーション、内容そのものの名前である。名前は分かり易くシンプルなほうがいい。ついでにいやらしくない名前の方が。東京では毎年、行政の支援のもとパフォーミング・アートのアーティストが、ホールの運営者に演目やカンパニーを売り込む「芸術見本市」という企画があり、定着している。芸術のほんの一領域なのに「芸術見本市」という名前がついてしまうのは、そのままパフォーミング・アートがこの国では力を持っているというあらわれだが、「アートデモ」はインフォメーション社会にもはやありながら、アート全体からみると、わざと見えないかのように避けられてきたかのような、メディア芸術に光をあて、そこで起きている新たなリアリティーを、まさにテクノロジー系にといっては最大の説得力を持った手段であり、オーディエンスにとっては発見と応用の可能性に頭を巡らせる期待感を高めるフォームである“デモンストレーション”いわゆるデモのかたちをとった、表現と創造と流通開発を一つのパッケージとした、新たなるアートイベントの形態であり、定着を求めるムーブメントの口火である。

まずは先導ケースをみてもらおう
→最初のアートデモのプログラムをデザインするにあたって、念頭に置いたのはただアクチャルなものをフィーチャーするのではなく、実は既に存在している成功事例やそこから生まれるダイナミズム、そうであってもブレークスルーが必要となっているという一目でわかる先導ケースを示すことで、先があることを認識してもらうことであった。



artdemo video ondemand
100kbpsのブロードバンドでお楽しみください
キーノートプレゼンテーション
椿昇+森脇裕之
→アートデモの最初の演目は、キーノート・デモンストレーションとして、逸早く事例を積み重ね、常にブレークスルーにつとめているアーティストにその場を任せることにした。既に現代芸術家としてインターナショナルにそのキャラクターとともに知られている椿昇と、紅白歌合戦という日本で最も大きい年越しミュージックイヴェントで国民的演歌歌手である小林幸子の電飾衣装を長年手がけるなど巨大なキネティック・インスタレーションをエンタテインメントの領域にまで作り上げるアルチザンでもある森脇裕之である。
昨年は日本最大の国際現代芸術展である横浜トリエンナーレの第一回を飾る巨大な飛蝗の造形物を高層ホテルの壁面にとまらせるなど、テクノロジーの限界をアートプロジェクトに求め続けてきた椿、そして工学技術を自分で組み立てて表現するアルチザンの不足を嘆きそれなら自身の手でと多摩美術大学でその育成に専念し始めた森脇、両者の結びつきはまさにメディア芸術もしくはサイエンスアートで、手が常に動き、実現化できるひとづくりの部分。
そこで、現在、2人が手がけているプロジェクトに巻き込んでいる学生に直接そのプロジェクトのプレゼンテーションをさせながら、それをフォローするかたちで2人がビジョンをかたるというデモが展開された。2人による、ひとづくりの最初の事例としているのは、大阪の万国博記念公園にある現代芸術学校のインターメディウム研究所。そこで、椿は学生とともに様々な電子制御が出来るロボットをテスターにして、電子技術を使った表現方法を誰もが理解し、作り出すことが出来る、メディアアートの種ともいうべき手法の開発を行うことで、人づくりを展開している。森脇はまさにソニーやパナソニックの商品開発研究所でのプロトタイプ作りと同じように、一から電子部品を組み立てながら新しい作品をどう開発して行くのかを提示、その理解と実践を促すためのモリワキットという作品工作キットを送り出している。デモでは、実際にそのキューブ状のロボット、ロボキューブを組み合わせ、プログラミングをしながら、最後には複数のロボットを多人数でいじることで音楽が形成されてゆく、ひとつの作品がたった1時間のデモのうちに組み上げられていった。このロボット、そして音楽を形成してゆくためのソフト、デモに登場した一つ一つのファクターがそれぞれもはや商品化されたり、実際に動き出しているという。作品ではなく、デモによって生まれる次の展開が既に2人にはあるのである。
椿と森脇のプレゼンテーションの後、今回の本題ともいうべき、国際的な評価が生まれ始めてきたアクチャルなアーティストによるデモンストレーションが開始された。

artdemo video ondemand
100kbpsのブロードバンドでお楽しみください
児玉幸子さんと竹野美奈子さんのデモでのビデオ ここをクリック
児玉幸子+竹野美奈子
→最初に登場したのは、児玉幸子と竹野美奈子。芸術コースでありながら、工学の理解と実践が得られる、日本で数少ない大学院である筑波大学でルームメートだった2人は、昨年のSIGGRAPHに
PROTRUDE、FLOWを出展、WIREDで見開きのグラビアで取り上げられるなど、今、最もインパクトのある作品を作り出した2人である。PROTRUDE、FLOWは、黒い磁性流体が外部の音に反応して様々な造形に変化する作品。一見するとイカ墨のスープのようなものが、音をたてた一瞬で菊の花のように尖形に華開く姿は誰もにとって驚きと、美しさを感じさせる。このシリーズにある、PULSAEはまさにバンケット・テーブルの皿の上に磁性流体のスープが盛り付けられ、そのインスタレーションに人が近づくと「スープ」が変幻自在の造形を生み出すもの。その美しいびっくり感は、世界共通で、世界各地様々なところで持ちかけられる展示において、それぞれどういう反応をしてくれるのか興味津々。これからも科学のふるまいを用いた、作品づくりをして行きたいとアピールした。

artdemo
video ondemand
100kbpsのブロードバンドでお楽しみください
minim++さんのデモでのビデオ
ここをクリック
minim++
/ 近森基+久納鏡子
→次に、近森基と久納鏡子が登場。2人の活動から、minim++ という新しい名前で活動することをデモした。近森と久納は、影を題材にした、インタラクティブ性のあるコンピュータ感を感じさせないインスタレーションが代表作。minim++になることによって、2人の属人性から離れた、様々なアーティストなどが関わりあう、芸術にとどまらない創造のプラットフォームが出来るのではとこれからの展開を++というキーワードでデモンストレーションした。おもちゃやインテリア、デザインなど、生活を取り巻くあらゆるものがメディア化してゆく中で、++
なヒントを与え、息吹を与えるものがアートによるアプローチであると説明、今までのインスタレーションの経験を活かし、ただポップアップするだけではなくインタラクションのある絵本を作り出して行くという提案事例を出しながら、メディア化する生活環境でのリアライゼーションの領域に、メディアアーティストが貢献できる場があり、そのアイディアを持っていることをアピールした。

artdemo
video ondemand
100kbpsのブロードバンドでお楽しみください
宇田敦子さんのデモでのビデオ
ここをクリック
宇田敦子
→独特のFLASHでの作品作りで、キヤノンデジタルクリエーターズコンテストに準グランプリとグランプリを連続受賞し、他にも数々の日本国内での同様のコンテストでここ2年受賞を続ける、宇田敦子。美大でインテリアを学ぶ一方、映画学校で自主制作を学び、デジタルムービーを志してIAMASに入った、他のメディア芸術家と異なる経験は、女性の日常生活の中にあるちょっとした物語を実写や手書き素材でFLASHを使い、ドラマやコメディーにする手法を確立し、日本的な情緒を持った世界のどこにも無い作品を作り続けている。宇田のデモは自身の作品集であるウェブページをナビゲートしながら、実際にそのドラマの数々を宇田の説明を聞きながら見てゆくシンプルなものであったが、それぞれのドラマを作り出した背景を語る宇田の語り口はまるで無声映画の講談ようであり、画面に展開する世界とインタラクションを見ながらどんどん惹きこまれて行く、全く新しいウェブ体験の面白さがデモによって発見されて行った。オーディエンスの満足度がデモの中で最も高かったように印象付けられるほどのはまりかたである。


クワクボリョウタ
→自身をデバイスアーティストと名乗る、クワクボリョウタ。いつも行く場所のひとつが秋葉原であるというクワクボは、自宅を工房に一から組み立てて電子作品を作り上げるアーティストであるとともにアルチザンでもある。
一つ一つの作品が、もはやプロダクトといってもいいくらい、デザインとしても洗練されているのと同様に、クワクボのウェブサイトは誰から見ても興味を引き立てるカタログとして機能している。このウェブサイトをベースに、今まで作ってきた作品や作品づくりの考え方をクワクボは展開した。手のひらサイズの大きさにLEDのディスプレーをつくりアニメーションが踊る、電子アクセサリー「ビットマン」(商品化済)など、無目的だけどかわいい、おもしろい、ものを作りたいという気持ちからアイディアが生まれ、自身の手で現実のものへとしてして行くという。それは、デバイスにとどまらず、ウェブ上でのプログラミングによる作品にもあらわれ、8×8のドット空間で何が描け、表現できるのかという、ミニマムなクリエイティブで遊ぶ参加型のJAVEアプリ「ビットハイク」という作品に例えばなっている。ミニマムな世界への反映としてビットの俳句という名を冠したこの作品、やはり、クワクボはものを作らないと気がすまなくなり、結局、ポータブルなゲーム機やアーケードゲーム機型の作品にして展開を広げてしまったとのこと。さらには、TVのRCA映像端子に挿すと中に入ったビットハイク作品を見ることが出来る電池大のデバイス(特許申請中)へと展開して行くなど、面白さによるアイディアの連鎖が、実物のものとしてしまうのだ。その連鎖がみえる語りにオーディエンスがひきつけられっきりだった。


artdemo video ondemand
100kbpsのブロードバンドでお楽しみください
フォトンさんのデモでのビデオ
ここをクリック
フォトン
→メディアアートとしてのエクスペリメントを企業バリューの向上に結び付るカンパニーも登場し始めている。アクチャルなアーティストのアートデモの最後となった、チーム・フォトンがそれである。フォトンはユニークなミッションを持ったゲーム会社「殺さない、戦わないゲームを作る」である。そのコンセプトに共鳴し、集まったゲームクリエーターたちは建築を修めた修士であったり、アンビエントなクラブイベントでVJをするグラフィックデザイナーなど、他領域の異才たち。
→その発想を伝わる形でプレゼンテーションするために、アートプロジェクトを活かそうとしている。
→携帯電話を誰もが持つ国で編み出した、携帯電話の着信とその波形に応じて光る服という、ちょっとしたインスタレーションは彼らのアイディアを一つのかたちにしたケースに過ぎない。
ゲーム開発の途上で作り上げたインタラクションを一つのアートプロジェクトにして、アイディアやフォトンが持つクリエイティビティーを示すということもやってのける。このリズムエンジンという、ネット上でのプロジェクトは、仮想の宇宙空間を浮遊体験するアプリケーションをダウンロード、その空間上での浮遊体験の痕跡としてサウンドを残し、同じアプリケーションを用いて浮遊する他のプレーヤーと言語を介さずにサウンドをセッションすることでコミュニケーションをはかり、音を楽しむというサイバースペースである。自身が持つ創造力やリアリティーを伝達するフィールドとして、アートを選んだフォトンの戦略は、能力をゲームの世界だけでなく、メディア教育やデザインなど他の領域にまで知られるようになり、その表現と能力を応用するフィールドが確実に広がりつつあるのだ。

Photo/U
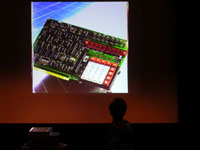
Photo/U

Photo/U
artdemo
video ondemand
100kbpsのブロードバンドでお楽しみください
後藤富雄さんのデモでのビデオ
ここをクリック
スペシャル・プレゼンテーション
後藤富雄
→アートデモに参加したアーティストたち自身が最も注目したのは、いわゆるアーティストによるデモではなかった。その注目のデモは、最後に行われた後藤富雄によるデモである。後藤はNECに長年勤めて半導体エンジニア。そのエンジニアリングの経歴はそのまま日本のパソコンの歴史そのものであった。スーパーコンピュータの時代に、日本ではじめて工作好きが手に入れることが出来る価格のパソコンを遊撃的なプロジェクトで送り出し、その後、DOS時代に日本のほとんどのシェアを占めるパソコンの開発を指揮、更には世界ではじめてのCD-ROM搭載のゲーム機を送り出した、現役でありながら伝説となっているエンジニアだ。一方で、ものづくりの発想力の好奇心から現代芸術家とプライベートで親交を持ち、インゴ・ギュンターなどにその技術やアイディアを提供してきた、エンジニアリングによるアートのサポーターでもある。その後藤がNECを55歳で退職、フリーランスのエンジニアという、独立した新人としてデモを行ってくれたのだ。
→NEC入社以来、身のまわりにあるテクノロジーの可能性を追い求め、そのアイディアと実行力で、プロジェクトを作り出してきた実績は、アーティストよりもときにはアーティスティックで、会社という組織の中にいても、どのような状態でも創造力が尽きなければ、自分の手でものを作り出し続けることが出来ることを身をもって物語ることで、オーディエンスに自身でもできることはもっとあるのではないかというエンパワーメントを与えてくれた。
→フリーになった今、NECという枠を超えて、日本やアメリカの様々なメーカーが持つテクノロジーを組み合わせることで、新しいプロダクトを作り出すことに最も注力しているという。ワンチップチューナーとマイクロハードディスク、そしてめがねに組み込める透過型ディスプレーで何が出来るか?後藤の頭から今も溢れる創造力は、より自由に何か新しいものが生み出されようとしてしている。その想像力とエンジニアリングに対する卓越した理解にオーディエンスもアーティストも魅了された。一方で後藤は、新しい発想と創造に対してひたむきな意欲を持っている後進を支援してゆきたいと表明、ものづくりとダイバシティーのある創造的コミットメントを求めようとしているアーティストとの新しいコラボレーションの可能性を提案して締めくくるのであった。
→テクノロジーそして動きや美学を絶え間なく融合し、創造力のサイクルをあげてゆくライブなメルティングポットとしてのムーブメントはこのようにささやかながらも、参加してくれた人たちの多くに何かを残してくれたことは確かであった。その証拠といってもいいだろうか、もう次のアートデモの準備が始まっている。
| artdemo top へ | coolstates home へ |
執筆=岡田 智博 info@coolstates.com
撮影=野口 伸吾(クレジットの無いもの全て) 、ユビキタスマン・カワイ(写真下U表示のもの)