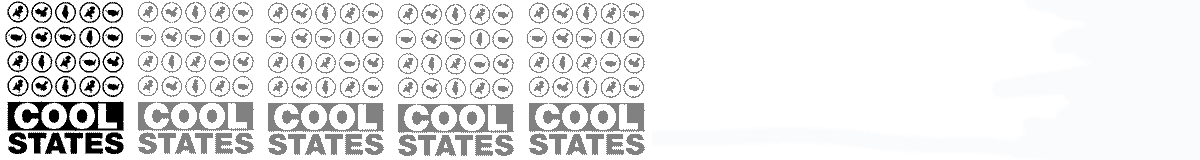September 20, 2002
アルスエレクトロニカ2002 みどころはペインステーションとゲームボーイZとインドの叡智
- cool states
- 10:34 PM
- Category: アルスエレクトロニカ02-08
明けても暮れてもデジタルが必要不可欠な現在、その時代にあったアートが自然と溶け込んでいるように思われるであろう。ところが「メディアアート」という言葉が日常に溢れているのに、実はそのトレンドを一堂に集めた巨大イベントは世界中で一つしか無い。そのたった一つのお楽しみが今年もcoolstates.comが週刊アスキーでレポートするアルス・エレクトロニカ・フェスティバル。
今回23年目を迎えるこのイベントは、中欧オーストリアの工業都市・リンツが、クラシックやオペラで超有名なウィーンに対抗するために、未来のカルチャーで目立とうと始めたもの。世界を見渡しても、新しいメディアがつくり出す新鮮なカルチャーシーンを体験させてくれる場がここだけという企画力で、現在益々世界中からアーティストやキュレーターが集結するユニークな場所として魅力を放っている。
2002年のアルス・エレクトロニカ・フェスティバルは9月7日から12日まで開催された。
この期間中、リンツの街中を会場に、朝から深夜までダブルどころかトリプルスケジュールといったイベントが満載されている。その内容は毎年決められるテーマに基づいたイベントやシンポジウムを中心に、同名の世界最大のメディアアートコンテストの表彰展覧会に、20万人が集まるドナウ河畔でのメディアアート花火大会など多岐にわたっている。
2002年のテーマは「アンプラグド」。地球規模のネットワークで結ばれることで繁栄し続ける欧米や東アジアの一方で、光当たらず接続されない(アンプラグドな)世界の存在に目を向けようというもの。例えば、昨年9月11日のNYテロもイスラムという宗教の問題より、欧米中心のITで一層引き離した発展から取り残された側からのメッセージとの視点が盛り込まれている。アフリカや中東でITを用いてカルチャーを作り出すキーパーソンを招き、「アフリカは多くの欧米人が考えるような『ITの暗黒大陸』では無く、自身のポップカルチャーや情報活用のネットワークを持った、乏しい環境の中でもデジタルクリエイティブやインターネットなどを工夫して生み出すローカルならではの豊かな多様さがある地域なのだ」(マリ国元文化大臣)という議論がシンポジウムを通じて行なわれていた。
今年の最新アートはオモシロ作品が満載
アルス・エレクトロニカ・フェスティバル最大の魅力はテーマイベントよりも、今のメディアアートを肌で体験し、それを創り出す魅力的なアーティストたちと実際に出会うことが出来ること。今年も上のグラビアのようにフレッシュで興味深いものが集まった。
会期中、毎晩開かれるライブはどうやって集めたのと思いたくなるようなユニークなアーティストたちによる見所だらけのもの。「ゲームボーイZオーケストラ」(159ページ)もその一つ。ポーランドのメディアアーティストたちによるこのバンド、「デジタルでアートする環境が恵まれてない分だけ身の回りのものを駆使して作品にするのは燃える」と語るのはリーダーのシャルソー・クジダ。クールな美女たちがメンバーとして演奏するように、ポーランドを中心とする東欧では、コンピュータのグラフィックやサウンド機能を研ぎ澄ますデモなどテックもののクリエイティブがかっこいいものとして認知され、いつも盛況になるクラブのイベントとして頻繁に開かれる世界があるのだ。
同名のコンテストのインタラクティブ部門の入選作が一堂に展示される「サイバーアート展」は、今のメディアアートを一気に体験できる贅沢な宝庫。期間中、作品展示のために出展アーティストたちが滞在、まるでアーティストたちのグローバルな合宿場という雰囲気でもある。入場すると目の前には「PainStation」が設置、その隣にPXL(159ページ)と同じく入選したPlay Station2用のゲーム「Rez」が振動ソファーによるラウンジでお出迎え、横の部屋にはインド人によるホーリーなインスタレーション(160ページ)空間やテーブルがかたかた鳴る(160ページ)部屋が連なるなど、メディアアートのテーマパークともいえるくらい楽しませてくれる今年の内容だった。
ジャパンオリジナルに脚光と期待が集まる
その中にあって、期待感とともに盛り上がったのが日本からのアート。オープニングアクトを、コンテンポラリーダンスとVJ、3Dモデリングによるコスチュームが融合する「メディアドライブ」を標榜するcell/66bが飾り、欧州のシーンには無いライブ感覚という衝撃を与える一方、プロダクトにも通じる洗練された作品を一人で創り出すクワクボリョウタには、引切り無しに同年代のヨーロッパ中からの若いアーティストたちが交流を求めていた。「欧州には無い日本の洗練と発想を持ったアーティストをもっと見たいし知りたい」と同フェスティバル代表のクリスチナ・スカロフが語るように、きっと日本には魅力的なものが控えているのではという期待が集まってきたアーティストやキュレーターから寄せられ、いつも議論になっているのが印象的であった。